家族信託」は、あなたの大切な財産(お金、家、土地など)を、将来、あなたや家族が困らないようにするための、とっても便利な仕組みなんです。
「もしもの時」と「大切な財産」
私たちは、誰でも年を取ったり、病気になったりして、自分で物事を決めるのが難しくなる日が来るかもしれません。そうなると、今まで当たり前にできていたことが、だんだん難しくなってきます。
銀行からお金をおろす
持っているアパートの家賃を管理する
介護施設に入るための契約をする
不動産を売ったり貸したり
などなど…
こんな時、自分で判断したり、手続きしたりするのが難しくなると、とても困ってしまいますよね。
もしかしたら、悪い人に騙されて、大切な財産をなくしてしまうなんてことにもなりかねません。
さらに、あなたが亡くなった後、残された家族が「この財産をどうしよう…」と困ってしまうこともあります。
特に、障がいのある子どもがいる場合や、何代にもわたって家族に財産を引き継いでいきたい場合など、通常の相続だけでは難しいケースもあります。
そんな「もしもの時」や「将来の財産管理・引き継ぎ」に備えて、あらかじめ準備しておくことができるのが、この家族信託なんです。
家族信託は「財産のバトンリレー」
家族信託を簡単に言うと、あなたの**大切な財産を、信頼できる家族に「託(たく)す」こと**です。
これは、あなたが持っている財産(例えば「家」)を、信頼できる家族(例えば「長男」)に「この家を、私のために、そして将来は孫のために、こんな風に管理してね」とお願いする仕組みです。
登場人物は、主に次の3人(または役割)です。
1. 委託者(いたくしゃ): 財産を「託す」人。あなた自身のことです。
2. 受託者(じゅたくしゃ): 財産を「託されて」管理する人。信頼できる家族(子ども、配偶者など)がなります。
3. 受益者(じゅえきしゃ): その財産から「利益を受け取る」人。最初はあなた自身が、そして将来的にはあなたの家族(配偶者や孫など)がなります。
まるで、財産の「バトンリレー」のようなイメージです。
あなたが元気なうち(委託者)に、「この財産(バトン)を、長男(受託者)に預けるね。
私のために使って、将来的には孫(受益者)に渡してあげてね」とお願いします。
長男(受託者)は、その財産(バトン)を、あなたが決めたルールに沿って管理します。あなたが認知症になっても、長男は財産を管理し続けられます。
そして、最終的には、その財産(バトン)が、あなたが望む「孫(受益者)」に引き継がれていく、という流れです。
あなた → 長男 → 孫
家族信託の大きなメリット
家族信託には、たくさんの良い点があります。
認知症になっても財産が凍結されない
これが一番大きなメリットかもしれません。もし、あなたが認知症などで判断能力がなくなってしまうと、あなたの銀行口座のお金は、家族であっても自由に引き出せなくなったり、不動産の売買ができなくなったりすることがあります。これを「財産凍結(ざいさんとうけつ)」と呼びます。
家族信託をしておけば、あなたが認知症になっても、あらかじめ決めておいた受託者(家族)が、あなたの財産を管理したり、必要な手続きを進めたりすることができます。たとえば、介護費用や医療費を支払ったり、不動産を売却して資金に換えたりすることが、スムーズにできるのです。
財産の引き継ぎ方を自由に決められる
普通の遺言書では、「この財産はAさんに、あの財産はBさんに」というように、一度きりの引き継ぎしか指定できません。
でも家族信託では、「私が亡くなったら、この家はまず妻に、妻が亡くなったら次は長男に、長男が亡くなったらさらにその子ども(孫)に」というように、何代にもわたって、財産の引き継ぎ方を細かく決めることができます。「うちの子どもは障がいがあるから、私が亡くなった後も、このお金で生活できるようにしてあげたい」といった、特別な事情にも対応できます。
争いごとが減る
相続でもめてしまうことは少なくありません。家族信託で財産の管理や引き継ぎのルールを明確にしておくことで、将来の家族間の争いを未然に防ぐことができます。あなたの願いがはっきりと形になるので、家族も納得しやすくなります。
面倒な手続きが少ない
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)と比べて、家庭裁判所(かていさいばんしょ)への手続きが少ないため、柔軟に財産を管理・運用できます。
家族信託の注意点(デメリット)
良い点が多い家族信託ですが、注意しておきたい点もあります。
最初に手続きや費用がかかる
家族信託を始めるには、専門家と相談しながら契約書(信託契約書といいます)を作ったり、不動産がある場合は登記の手続きをしたりする必要があります。これには、それなりのお金と手間がかかります。
万能ではない
家族信託は、財産の管理や引き継ぎにはとても強い力を発揮しますが、
あなたの医療行為に対する同意や、介護施設への入所契約など、「あなたの身体に関わること」はカバーできません。
任意後見制度と組み合わせて手続きをすることが大事になってきます。
受託者(財産を管理する家族)の負担
受託者になった家族は、財産をきちんと管理し、お金の出入りを記録したり、税金の手続きをしたりする責任があります。
信頼できる家族だからこそ任せられるのですが、その家族に負担がかかることも理解しておく必要があります。
税金の専門知識が必要になることもある
家族信託をしたからといって、税金が安くなるわけではありません。贈与税(ぞうよぜい)や所得税(しょとくぜい)、相続税(そうぞくぜい)など、税金の取り扱いが複雑になる場合もあるので、税理士(ぜいりし)など専門家に相談することが大切です。
家族信託には、どのくらいお金がかかるの?
専門家(司法書士、弁護士など)に依頼する費用
家族信託は、専門的な知識が必要なため、多くの場合、司法書士や弁護士に相談して手続きを進めます。
コンサルティング費用+契約書作成費用
信託契約の内容を検討し、契約書を作るための費用です。
財産の種類や規模、信託の内容の複雑さによって大きく変わりますが、
20万円から50万円程度が目安となることが多いです。
より複雑なケースでは、それ以上かかることもあります。
信託契約書を公正証書にする費用
契約内容を公的に証明するため、公正役場(こうしょうやくば)で「公正証書(こうせいしょうしょ)」にすることが一般的です。
公正証書作成手数料: 契約の目的となる財産の額によって手数料が変わりますが、一般的には数万円から数十万円かかります。
例えば、信託する財産の価値が1000万円なら数万円、1億円なら数十万円、といったイメージです。
不動産がある場合の費用
信託する財産の中に不動産(家や土地)がある場合は、その不動産の名義を「受託者」に変える登記(とうき)が必要です。
登録免許税(とうろくめんきょぜい)
不動産の価値に応じてかかる税金です。不動産の固定資産評価額(こていしさんひょうかがく)の0.3%〜0.4%程度がかかります。
例えば、評価額が2000万円の家なら、6万円〜8万円程度です。
司法書士への登記手続き費用
登記を司法書士に依頼する場合の費用です。
数万円から10万円程度が目安です。
その他
税理士への相談費用
税金について相談する場合にかかります。
信託契約後の管理費用
受託者(財産を管理する家族)が専門家に継続的なサポートを依頼する場合などにかかる費用です。
これらの費用は、信託する財産の種類や量、内容の複雑さ、依頼する専門家によって大きく異なります。まずは、いくつかの専門家に相談して、見積もりを出してもらうことが大切です。
家族信託が必要な人はどんな人?
認知症対策をしたい方
自分や家族が将来認知症になった時に、財産が凍結されて困らないようにしたい方。
障がいのある子どもがいる方
自分が亡くなった後も、その子どもが安心して暮らせるよう、長期的に財産管理をしてほしい方。
特定の財産(アパートや賃貸物件など)を、将来も有効活用していきたい方
家族に引き継いで、管理や運用を任せたい方。
再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる方
財産をどのように引き継ぐか、複雑な場合に。
事業を承継したい方
会社の株式などを後継者にスムーズに引き継ぎたい場合。
通常の遺言書だけでは対応できない、複雑な財産の引き継ぎをしたい方
家族信託を始めるには、どこに相談すればいい?
家族信託は、専門的な知識が必要な制度です。そのため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
司法書士(しほうしょし)
契約書の作成や不動産の登記手続きなど、法律的な手続きに詳しいです。
弁護士(べんごし)
幅広い法律問題に対応でき、紛争予防の観点からもアドバイスがもらえます。
税理士(ぜいりし)
税金に関わる問題について、専門的なアドバイスがもらえます。
信託銀行(しんたくぎんこう)
会社が信託業務を行っていますが、費用が高額になる傾向があります。
まずは、「話を聞いてみたい」という気持ちで、気軽に相談してみると良いでしょう。
費用については、相談時にしっかり確認し、見積もりをもらうことをお忘れなく。
まとめ
家族信託は、あなたの大切な財産を、あなたが元気なうちに、信頼できる家族に託し、将来の不安に備えるための強力な仕組みです。
認知症対策や、何代にもわたる財産の引き継ぎ、家族間の争いを防ぐなど、多くのメリットがありますが、その分、初期費用や手続きの手間がかかるという注意点もあります。
ご自身の状況に合わせて、専門家とよく相談し、最適な方法を選ぶことが大切です。
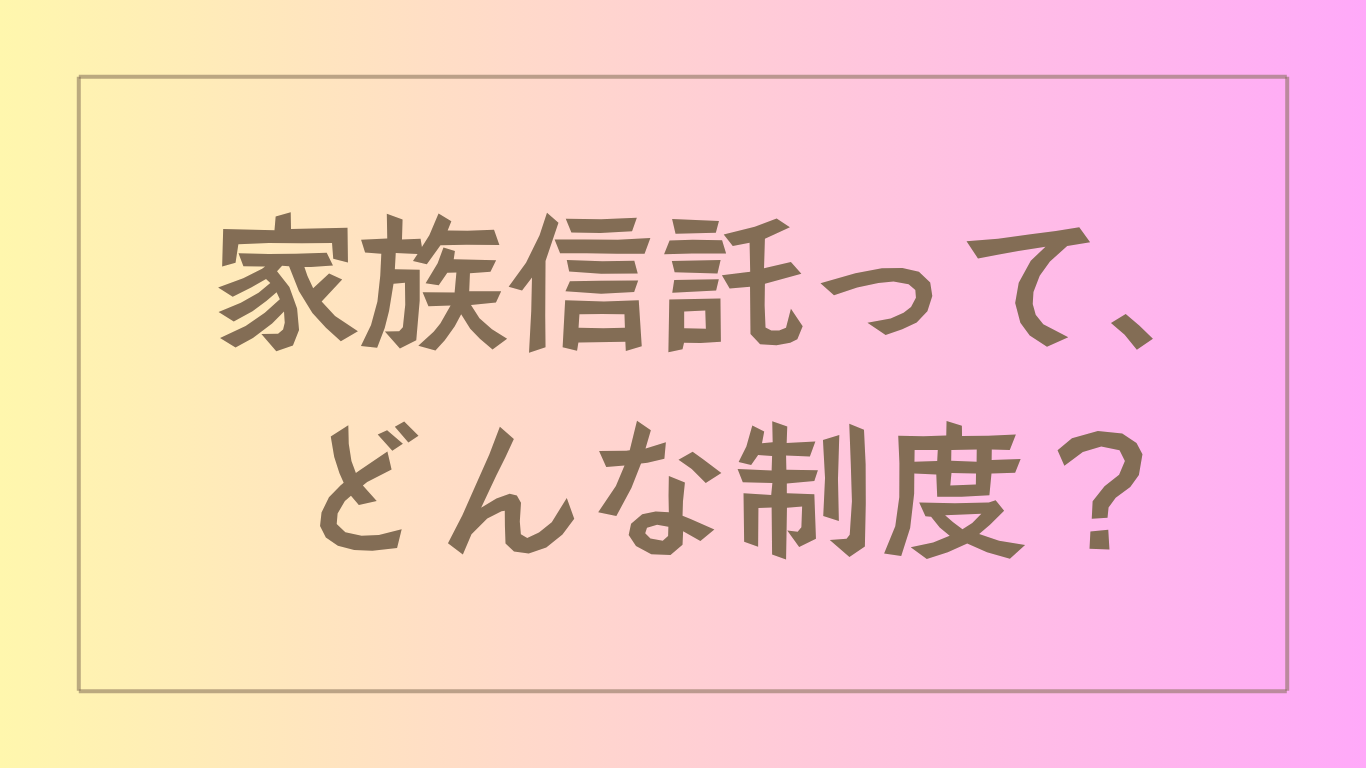

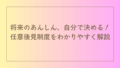
コメント