「年金分割」って何?離婚で年金が半分に?あなたの老後を左右する大切な話
結婚している間、夫婦はそれぞれ異なる形で家計を支えていることが多いですよね。でも、もし離婚することになったら、将来もらえる年金額はどうなるんだろう?そんな不安を感じる方もいるかもしれません。
実は、離婚後の生活を安定させるために、**「年金分割」**という大切な制度があります。これは、結婚していた期間に夫婦で協力して築いた年金記録を、離婚時に公平に分け合う仕組みのこと。
今回は、この年金分割について、なぜ必要なのか、どんな年金が対象になるのか、そしてどうやって分割するのかを、わかりやすく解説していきます。
なぜ年金分割が必要なの?〜「夫婦の協力」を形にする制度〜
結婚期間中、夫婦は様々な形で協力し合って生活しています。例えば、こんなケースが考えられます。
- 夫が会社員、妻が専業主婦だった場合 夫の給与から厚生年金保険料が支払われ、夫名義の年金記録が積み上がります。しかし、妻が家庭を支え、家事や育児に専念したことで、夫は安心して働くことができ、年金を積み立てられたとも言えますよね。もし離婚すると、妻は自身の年金記録が少ないため、将来受け取れる年金額が夫に比べて大幅に少なくなる可能性があります。
- 夫婦共働きで、夫の収入が妻より多かった場合 夫婦ともに厚生年金に加入していても、収入が多い方の年金記録が多くなります。離婚後、収入が少なかった方が将来受け取る年金額が不利になる可能性があります。
このように、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた年金は、どちらか一方の名義になっていることがほとんどです。年金分割は、こうした年金受給額の不均衡を是正し、離婚後の生活の安定を図ることを目的としています。つまり、夫婦の協力関係を年金にも反映させるための大切な制度なんです。
どの年金が対象になるの?
年金分割の対象となるのは、主に以下の年金です。
- 会社員や公務員が加入する「厚生年金」
- 私立学校教職員等が加入する「私学共済制度」
国民年金(基礎年金)は対象外です。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、夫婦の協力関係による年金格差が生じにくいという考え方に基づいています。
どうやって年金を分割するの?2つの方法
年金分割には、主に以下の2つの方法があります。
1.合意分割(夫婦で話し合って決める方法)
これは、夫婦の合意、または裁判所の手続きによって分割割合を決める方法です。
- 対象期間: 2008年3月31日以前の婚姻期間における厚生年金記録も対象になります。
- 分割の割合: 夫婦それぞれの厚生年金の標準報酬総額(給与や賞与の合計額)を合計し、その範囲内で**最大50%**まで分割できます。例えば、夫の年金記録の標準報酬が1000万円、妻が200万円だった場合、合計1200万円を夫婦で最大600万円ずつ分け合うことが可能です。
- 手続き:
- 年金情報通知書の請求: まず、年金事務所でそれぞれの年金記録や分割対象期間の情報が記載された「年金分割のための情報通知書」を取得します。
- 夫婦での話し合い: 通知書の内容を基に、夫婦間で分割割合について話し合い、合意します。
- 公正証書の作成または調停・裁判: 合意した内容を公正証書にまとめるか、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判、裁判で決定します。
- 年金事務所での手続き: 最終的に決定した内容を年金事務所に提出し、手続きを行います。
2.3号分割(自動的に半分になる方法)
これは、主に専業主婦(主夫)だった期間の厚生年金を、相手の同意なしに自動的に半分に分割できる制度です。
- 対象期間: 2008年4月1日以降の婚姻期間で、国民年金の第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されていた配偶者)であった期間が対象です。
- 分割の割合: 第3号被保険者の配偶者の厚生年金記録の半分が自動的に分割されます。相手の同意は不要です。
- 手続き:
- 年金事務所での手続き: 第3号被保険者だった方が単独で年金事務所に請求するだけで手続きが可能です。
- 必要書類: 戸籍謄本や年金手帳などが必要です。
【例で見てみよう!】
- 合意分割の例: 夫が会社員で、2000年から2020年まで勤務。妻は夫と結婚後、2005年までは会社員として働き、2006年から専業主婦になったとします。 この場合、2000年~2005年の共働き期間、および2006年~2020年の専業主婦期間の両方で合意分割の対象となります。例えば、夫婦の話し合いで、夫の年金記録のうち婚姻期間に対応する部分の40%を妻に分割することに合意した場合、その割合で年金が分割されます。
- 3号分割の例: 夫が会社員で、2010年に結婚し、妻はずっと専業主婦(第3号被保険者)だったとします。 2010年の結婚から離婚までの期間が2008年4月1日以降なので、妻は夫の厚生年金記録のうち、この期間の半分を夫の同意なしに受け取ることができます。
いつ手続きするの?
年金分割の手続きは、離婚が成立した日の翌日から原則として2年以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として年金分割の請求はできなくなりますので注意が必要です。
まとめ
年金分割は、離婚時に婚姻期間中の厚生年金記録を公平に分け合う制度です。
- 目的: 夫婦の協力で築いた年金原資の公平な分配と、離婚後の生活の安定。
- 対象: 主に会社員や公務員の厚生年金(国民年金は対象外)。
- 方法:
- 夫婦の合意が必要な「合意分割」(2008年3月31日以前の期間も対象、最大50%まで)。
- 2008年4月1日以降の期間の第3号被保険者が単独で請求できる「3号分割」(自動的に半分)。
- 期限: 手続きは離婚後2年以内に行う必要があります。
年金分割は、離婚後の生活設計において非常に重要な制度です。ご自身の状況に合わせて、どの分割方法が適切か、また具体的な手続きについて、年金事務所や専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
結婚している間、夫婦はそれぞれ異なる形で家計を支えていることが多いですよね。でも、もし離婚することになったら、将来もらえる年金額はどうなるんだろう?そんな不安を感じる方もいるかもしれません。
実は、離婚後の生活を安定させるために、**「年金分割」**という大切な制度があります。これは、結婚していた期間に夫婦で協力して築いた年金記録を、離婚時に公平に分け合う仕組みのこと。
今回は、この年金分割について、なぜ必要なのか、どんな年金が対象になるのか、そしてどうやって分割するのかを、わかりやすく解説していきます。
なぜ年金分割が必要なの?〜「夫婦の協力」を形にする制度〜
結婚期間中、夫婦は様々な形で協力し合って生活しています。例えば、こんなケースが考えられます。
- 夫が会社員、妻が専業主婦だった場合 夫の給与から厚生年金保険料が支払われ、夫名義の年金記録が積み上がります。しかし、妻が家庭を支え、家事や育児に専念したことで、夫は安心して働くことができ、年金を積み立てられたとも言えますよね。もし離婚すると、妻は自身の年金記録が少ないため、将来受け取れる年金額が夫に比べて大幅に少なくなる可能性があります。
- 夫婦共働きで、夫の収入が妻より多かった場合 夫婦ともに厚生年金に加入していても、収入が多い方の年金記録が多くなります。離婚後、収入が少なかった方が将来受け取る年金額が不利になる可能性があります。
このように、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた年金は、どちらか一方の名義になっていることがほとんどです。年金分割は、こうした年金受給額の不均衡を是正し、離婚後の生活の安定を図ることを目的としています。つまり、夫婦の協力関係を年金にも反映させるための大切な制度なんです。
どの年金が対象になるの?
年金分割の対象となるのは、主に以下の年金です。
- 会社員や公務員が加入する「厚生年金」
- 私立学校教職員等が加入する「私学共済制度」
国民年金(基礎年金)は対象外です。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、夫婦の協力関係による年金格差が生じにくいという考え方に基づいています。
どうやって年金を分割するの?2つの方法
年金分割には、主に以下の2つの方法があります。
1.合意分割(夫婦で話し合って決める方法)
これは、夫婦の合意、または裁判所の手続きによって分割割合を決める方法です。
- 対象期間: 2008年3月31日以前の婚姻期間における厚生年金記録も対象になります。
- 分割の割合: 夫婦それぞれの厚生年金の標準報酬総額(給与や賞与の合計額)を合計し、その範囲内で**最大50%**まで分割できます。例えば、夫の年金記録の標準報酬が1000万円、妻が200万円だった場合、合計1200万円を夫婦で最大600万円ずつ分け合うことが可能です。
- 手続き:
- 年金情報通知書の請求: まず、年金事務所でそれぞれの年金記録や分割対象期間の情報が記載された「年金分割のための情報通知書」を取得します。
- 夫婦での話し合い: 通知書の内容を基に、夫婦間で分割割合について話し合い、合意します。
- 公正証書の作成または調停・裁判: 合意した内容を公正証書にまとめるか、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判、裁判で決定します。
- 年金事務所での手続き: 最終的に決定した内容を年金事務所に提出し、手続きを行います。
2.3号分割(自動的に半分になる方法)
これは、主に専業主婦(主夫)だった期間の厚生年金を、相手の同意なしに自動的に半分に分割できる制度です。
- 対象期間: 2008年4月1日以降の婚姻期間で、国民年金の第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されていた配偶者)であった期間が対象です。
- 分割の割合: 第3号被保険者の配偶者の厚生年金記録の半分が自動的に分割されます。相手の同意は不要です。
- 手続き:
- 年金事務所での手続き: 第3号被保険者だった方が単独で年金事務所に請求するだけで手続きが可能です。
- 必要書類: 戸籍謄本や年金手帳などが必要です。
【例で見てみよう!】
- 合意分割の例: 夫が会社員で、2000年から2020年まで勤務。妻は夫と結婚後、2005年までは会社員として働き、2006年から専業主婦になったとします。 この場合、2000年~2005年の共働き期間、および2006年~2020年の専業主婦期間の両方で合意分割の対象となります。例えば、夫婦の話し合いで、夫の年金記録のうち婚姻期間に対応する部分の40%を妻に分割することに合意した場合、その割合で年金が分割されます。
- 3号分割の例: 夫が会社員で、2010年に結婚し、妻はずっと専業主婦(第3号被保険者)だったとします。 2010年の結婚から離婚までの期間が2008年4月1日以降なので、妻は夫の厚生年金記録のうち、この期間の半分を夫の同意なしに受け取ることができます。
いつ手続きするの?
年金分割の手続きは、離婚が成立した日の翌日から原則として2年以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として年金分割の請求はできなくなりますので注意が必要です。
まとめ
年金分割は、離婚時に婚姻期間中の厚生年金記録を公平に分け合う制度です。
- 目的: 夫婦の協力で築いた年金原資の公平な分配と、離婚後の生活の安定。
- 対象: 主に会社員や公務員の厚生年金(国民年金は対象外)。
- 方法:
- 夫婦の合意が必要な「合意分割」(2008年3月31日以前の期間も対象、最大50%まで)。
- 2008年4月1日以降の期間の第3号被保険者が単独で請求できる「3号分割」(自動的に半分)。
- 期限: 手続きは離婚後2年以内に行う必要があります。
年金分割は、離婚後の生活設計において非常に重要な制度です。ご自身の状況に合わせて、どの分割方法が適切か、また具体的な手続きについて、年金事務所や専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
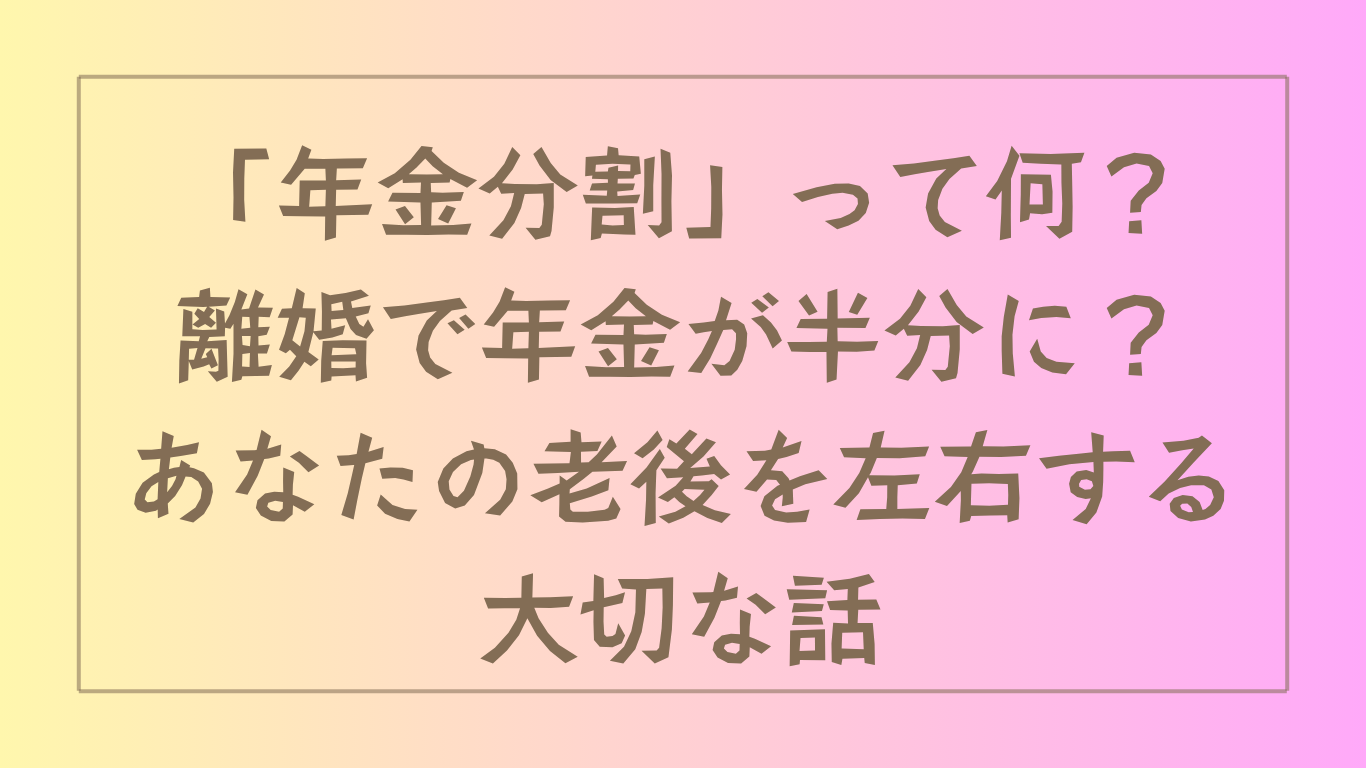
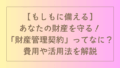
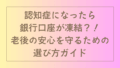
コメント