「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」という言葉、なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんね。でも、これは将来、もしあなたが自分で物事を決めるのが難しくなった時に、あなた自身や大切な家族を守るための、とても大事な仕組みなんです。
「もしもの時」に備えて、あらかじめ準備しておくことができる「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」
「もしもの時」って、どんな時?
私たちはみんな、いつまでも今のまま元気でいられるとは限りません。年を取って体が不自由になったり、病気で頭がぼんやりしてしまったりすることもあります。そうすると、今まで当たり前にできていたことが、だんだん難しくなってくるかもしれません。
たとえば、こんなことです。
- 銀行でお金をおろすこと毎月の家賃や光熱費を払うこと
- 病院の入院手続きや治療の契約をすること
- 介護施設に入るための手続きをすること
- 持っている家や土地をどうするか決めること
こんな時、自分で判断したり、手続きしたりするのが難しくなると、とても困ってしまいますよね。
もしかしたら、悪い人に騙されて、大切な財産をなくしてしまうなんてことにもなりかねません。
そんな「もしもの時」に備えて、あらかじめ準備しておくことができるのが、この任意後見制度なんです。
「任意後見制度」は、あなたの「願い」を叶える制度
この制度は、あなたがまだ元気なうちに、「将来、もし自分で判断できなくなったら、こんなことをしてほしい」という願いを、あらかじめ契約という形で決めておくものです。
普通の生活ではあまり「契約」という言葉を使うことはありませんが、これはあなたが「この人になら任せたい」という人(これを「任意後見人(にんいこうけんにん)」と呼びます)と、「将来、こういうことをお願いします」という約束をすることだと考えてください。
そして、実際にあなたが自分で判断できなくなった時に、その「任意後見人」が、あなたの代わりに、あらかじめ約束したことを行ってくれるようになるのです。
—
「任意後見制度」のポイントを簡単にご説明!
いくつか大切なポイントがあるので、もう少し詳しく見ていきましょう。
「元気なうち」に準備する
これが一番大事なことです。任意後見制度は、あなたがまだ自分の意思で物事を決められる、元気なうちにしか契約できません。なぜなら、あなたが「この人に任せたい」という気持ちを、はっきりと伝える必要があるからです。
誰に頼む?「任意後見人」ってどんな人?
任意後見人になれる人に、特に決まりはありません。
あなたの家族(子ども、兄弟など)でも良いですし、親しい友人、信頼できる専門家(弁護士や司法書士など)でも大丈夫です。
大切なのは、「この人になら、自分の大切なことや財産を任せられる」と心から思える人を選ぶことです。
どんなことを頼めるの?
どんなことをお願いするかは、あなたが自由に決めることができます。
たとえば、
- 銀行からお金を引き出して、生活費や医療費を支払うこと
- 年金を受け取ること
- 介護サービスの手続きをすること
- 入院の手続きや費用の支払い
- 持っている不動産(家や土地)の管理や売買
- もし詐欺などに遭いそうになったら、助けてもらうこと
など、あなたの生活に関わるさまざまなことを頼むことができます。
ただし、どんなことでも頼めるわけではなく、あくまであなたの生活や財産を守るためのこと、という範囲があります。
どうやって契約するの?
任意後見契約は、「公正証書」という特別な書類で作る必要があります。
これは、法律のプロである公証人(こうしょうにん)という人が、あなたと任意後見人になる人の約束の内容を正確に書き記し、それが本物であることを証明してくれる書類です。
なぜ公正証書が必要かというと、後で「言った」「言わない」のトラブルにならないように、そしてあなたが本当にその内容に納得して契約したことを、国が認める形にするためです。
これがあることで、あなたの願いがしっかりと守られるようになります。
いつから始まるの?
任意後見契約は、元気なうちに作りますが、実際に任意後見人が動き出すのは、あなたが自分で判断することが難しくなってからです。
「判断することが難しくなった」というのは、お医者さんの診断などをもとに判断されます。そして、家庭裁判所というところが、「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」という人を選んでくれます。
この「任意後見監督人」は、任意後見人があなたの願い通りに、ちゃんと仕事をしているかを見守る役割です。つまり、任意後見人が勝手なことをしないように、二重でチェックする仕組みになっているので、より安心できますね。
任意後見制度には、どのくらいお金がかかるの?
任意後見制度を利用するには、いくつかお金がかかることがあります。具体的に見ていきましょう。
契約を結ぶ時(元気なうち)にかかる費用
公正証書を作る手数料(公証役場での費用)
これは、任意後見契約を公正証書にするために必要な費用です。契約の内容によって少し変わることもありますが、一般的には**1万円から2万円程度**です。これに加えて、契約書の謄本(写し)の費用などが数百円かかります。
専門家(弁護士、司法書士など)に依頼する場合の費用
ご自分で公正証書の作成手続きを進めることもできますが、専門家にお願いすると、契約の内容を相談したり、必要な書類を準備してもらったりと、スムーズに進めることができます。この場合の費用は、依頼する内容や事務所によって大きく異なりますが、だいたい**5万円から20万円程度**が目安になります。
実際に後見が始まった後にかかる費用
あなたが自分で判断することが難しくなり、任意後見人が実際に働き始めてからかかる費用です。
任意後見監督人の報酬(費用)
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックする人です。この任意後見監督人には、毎月お給料のような「報酬」を支払う必要があります。
この報酬は、あなたの財産状況によって変わりますが、月額1万円から3万円程度が一般的です。これは、家庭裁判所が金額を決めてくれます。
* **任意後見人の報酬(費用)**:
あなたが選んだ任意後見人が、家族や親しい友人で、無報酬で引き受けてくれる場合は、この費用はかかりません。しかし、弁護士や司法書士などの専門家を任意後見人にした場合は、その専門家に対して毎月報酬を支払うことになります。
この報酬も、あなたの財産状況や、任意後見人が行う仕事の内容によって変わりますが、**月額2万円から5万円程度**が目安となることが多いです。こちらも、家庭裁判所が金額を考慮します。
このように、任意後見制度には、契約時と、実際に後見が始まった後の両方で費用がかかる可能性があります。特に、専門家を任意後見人に選ぶ場合は、月々の報酬が発生することを覚えておきましょう。
任意後見制度のメリットって?
この制度を使うことで、次のような良いことがあります。
あなたの「願い」が叶う
自分で「こうしてほしい」と決めた通りに、あなたの生活や財産が守られます。
信頼できる人に任せられる
自分で選んだ人だから、安心して任せることができます。自分で「こうしてほしい」と決めた通りに、あなたの生活や財産が守られます。
もしもの時に備えられる
将来への不安を減らし、安心して暮らせます。
家族の負担を減らせる
あなたが困った時に、家族がどうしていいか分からず困ってしまう、という状況を防ぐことができます。家族にとっても安心材料になります。
詐欺などから身を守れる
判断能力が低下した人につけ込む悪い人から、あなたの財産を守る強力な盾になります。
法定後見制度との違いは?
よく似た制度に「法定後見制度」がありますが、一番の違いは「いつ、誰が決めるか」です。
- 任意後見制度:
- いつ? 本人の判断能力があるうちに、元気なときに。
- 誰が? 本人が、自分で任意後見人を選び、契約内容を決めます。
- 法定後見制度:
- いつ? 本人の判断能力がすでに不十分になった後に。
- 誰が? 家庭裁判所が、後見人を選任します。本人の希望が通らない場合もあります。
つまり、任意後見制度は「自分のことは自分で決めたい」という意思を、将来にわたって実現するための制度なんです。
どんな人が任意後見人になれるの?
任意後見人になれる人に特別な資格は必要ありません。**信頼できる人であれば、家族や親族はもちろん、友人、知人でもなることができます。**弁護士や司法書士などの専門家を依頼することも可能です。
ただし、未成年者や破産者など、法律で定められた人は任意後見人になることができません。
任意後見契約を結ぶには?
任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことで、法的な効力が非常に高いのが特徴です。
契約を結ぶ際には、任意後見人になってくれる人と一緒に公証役場へ行き、どんなサポートをお願いしたいのか、具体的に話し合って契約内容を決めます。
まとめ
任意後見制度は、将来への不安を解消し、「自分らしい人生を最後まで送りたい」という願いを叶えるための心強い味方です。
まだ早い、と思わずに、元気なうちに将来のことを考えておくことは、自分自身のためだけでなく、大切な家族のためにもなります。ぜひ一度、この制度について家族と話し合ってみたり、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
—
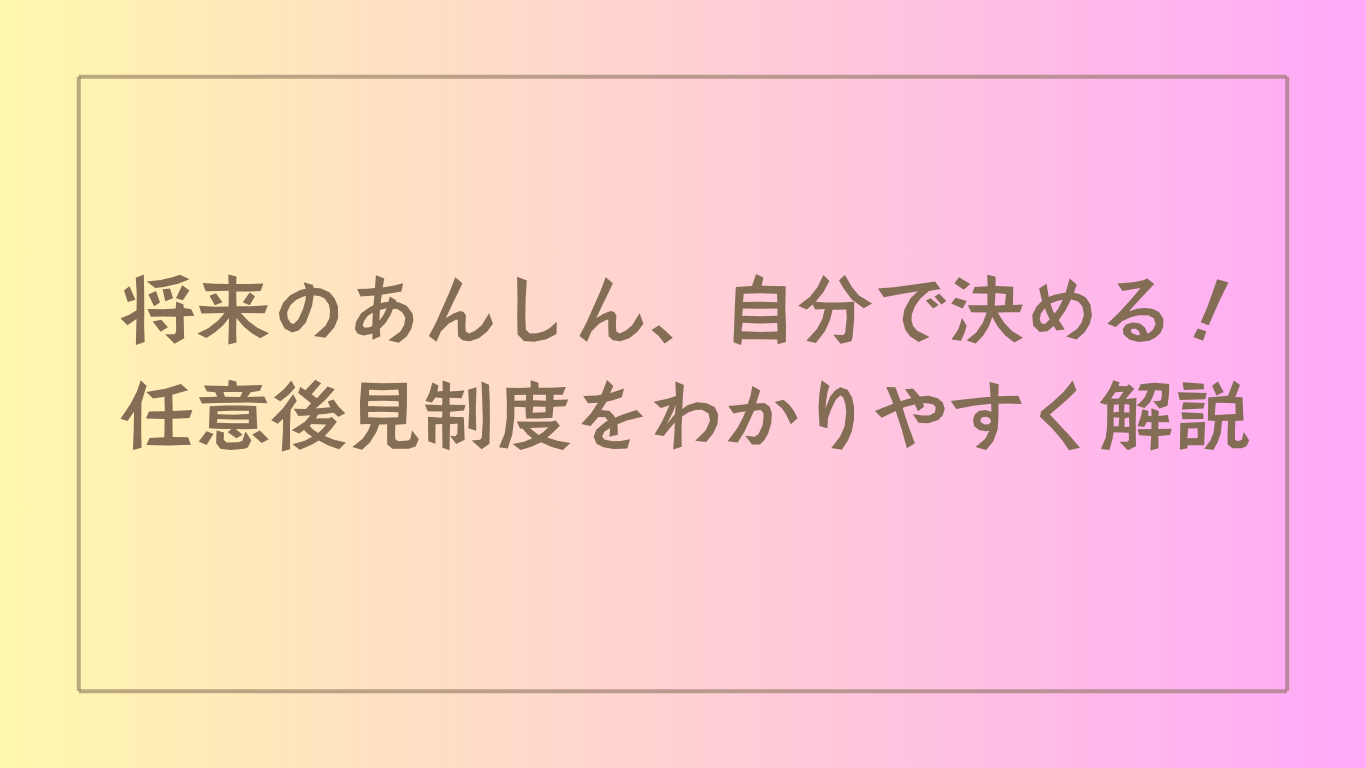
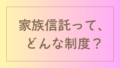
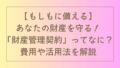
コメント