「財産管理契約(ざいさんかんりけいやく)」は、もしあなたが病気やケガで一時的に動けなくなったり、判断能力が少し衰え始めた時に、あなたの大切な財産(お金、年金、家賃など)を、信頼できる人に管理してもらうための、とっても身近な「約束」なんです。
今回は、そんな財産管理契約について、どんな時に役立つのか、どうやって使うのか、気になる費用まで、わかりやすく解説していきます。
「もしもの時」って、どんな時?
私たちは誰でも、急な病気や事故で一時的に入院が必要になったり、体が不自由になったりすることがあります。また、年を重ねると、判断能力が少しずつ衰え始めて、「銀行でお金をおろすのが面倒になってきたな…」「毎月の支払いを忘れてしまうことがあるな…」と感じるようになるかもしれません。
こんな時、自分で判断したり、手続きしたりするのが難しくなると、とても困ってしまいますよね。
例えば、こんな状況に直面するかもしれません。
- 入院中の食費や日用品の購入費が必要なのに、お金がおろせない…
- 毎月の家賃や光熱費の引き落とし口座にお金が足りない…
- 介護サービスの費用を支払いたいけど、銀行に行けない…
こんな時に「誰かに代わりにお願いしたいな」と思うことはありませんか?そんな時に役立つのが、この財産管理契約なんです。
財産管理契約は「一時的なお手伝い」の約束
財産管理契約は、あなたがまだ自分で物事を決めることができるうちに、「もし、私が一時的に財産を管理できなくなったら、この人に代わりにお願いします」と約束しておくことです。
これは、あなたが「この人になら任せたい」という人(これを「受任者(じゅにんしゃ)」と呼びます)と、「こんなことをお願いします」という約束をすることだと考えてください。
そして、実際にあなたが財産管理を自分でできなくなった時に、その「受任者」が、あなたの代わりに、あらかじめ約束した財産の管理を行ってくれるようになるのです。
財産管理契約の基本をチェック!
いくつか大切なポイントがあるので、もう少し詳しく見ていきましょう。
1.「元気なうち」に準備する
これが一番大事なことです。財産管理契約は、あなたがまだ自分の意思で物事を決められる、元気なうちにしか契約できません。なぜなら、あなたが「この人に任せたい」という気持ちを、はっきりと伝える必要があるからです。
2.誰が「受任者」になれるの?
受任者になれる人に、特別な資格は必要ありません。あなたの**家族(子ども、兄弟など)でも良いですし、親しい友人、または信頼できる専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)**でも大丈夫です。
大切なのは、「この人になら、自分の大切なお金や財産を任せられる」と心から思える人を選ぶことです。
3.どんなことを頼めるの?
どんなことをお願いするかは、あなたが自由に決めることができます。例えば、
- 銀行からお金を引き出して、生活費や医療費、介護費を支払うこと
- 年金や家賃の受け取り
- 医療費や介護サービスの費用の管理
- 預貯金通帳や印鑑、キャッシュカードなどの保管
- 各種税金や公共料金の支払い
- 不動産を所有している場合は、その管理(固定資産税の支払いなど)
など、あなたの生活に関わる、お金や財産に関するさまざまなことを頼むことができます。ただし、あくまで「財産の管理」という範囲になります。
4.どうやって契約するの?
財産管理契約は、口約束でも法的には有効ですが、後で「言った」「言わない」のトラブルにならないように、書面(契約書)にしておくことが強く推奨されます。さらに、できれば「公正証書(こうせいしょうしょ)」という特別な書類で作るのが一番安心です。
公正証書にすることで、法律のプロである公証人(こうしょうにん)という人が、あなたと受任者になる人の約束の内容を正確に書き記し、それが本物であることを証明してくれます。これにより、後々のトラブルを防ぎ、あなたの意思がしっかりと守られるようになります。
財産管理契約のメリットって?
この制度を使うことで、次のような良いことがあります。
- 柔軟に対応できる: あなたの体調や状況に合わせて、必要な時だけ財産管理を任せることができます。
- あなたの「願い」が叶う: 自分で「こうしてほしい」と決めた通りに、あなたの財産が管理されます。
- 信頼できる人に任せられる: 自分で選んだ人だから、安心して任せることができます。
- もしもの時に備えられる: 将来の急な体調変化などによる不安を減らし、安心して暮らせます。
- 家族の負担を減らせる: あなたが一時的に財産管理できなくなった時に、家族がどうしていいか分からず困ってしまう、という状況を防ぐことができます。
- 費用を抑えられる場合がある: 他の制度より費用を抑えられるケースもあります。
財産管理契約の注意点(デメリット)
良い点が多い財産管理契約ですが、注意しておきたい点もあります。
1.本人の判断能力がなくなると使えない
これが一番重要な注意点です。財産管理契約は、あくまであなたが自分で物事を判断できる能力がある間に有効な契約です。もし、あなたが認知症などで完全に判断能力を失ってしまった場合、この契約は解除されてしまい、代わりに「法定後見制度」を利用する必要が出てきます。
財産管理契約は、一時的な病気や入院などで財産管理が一時的に難しくなった時や、判断能力が少し衰え始めた時に有効な「予防策の第一段階」と考えると良いでしょう。
2.受任者の権限に限界がある
財産管理契約で任せられるのは、あくまで「財産の管理」が中心です。例えば、あなたが病気になった時に、受任者があなたの代わりに「手術に同意する」といった医療行為の同意や、「介護施設への入居契約を結ぶ」といった身の回りのことに関する契約は、基本的にはできません。これらをカバーするには、別の制度(任意後見制度など)と組み合わせる必要があります。
3.信頼できる人を選ぶのが重要
受任者があなたの財産を管理するため、その人が誠実に業務を行ってくれることが大切です。もし受任者が財産を私的に流用したり、不適切な管理をしたりした場合、トラブルに発展する可能性があります。
財産管理契約にかかるお金は?
財産管理契約にかかる費用は、誰に、何を、どのくらいの期間お願いするかによって大きく変わります。
1.契約を結ぶ時(元気なうち)にかかる費用
- 公正証書を作る手数料(公証役場での費用): 契約を公正証書にする場合にかかります。契約の内容やお願いする財産の額によって変わりますが、一般的には1万円から数万円程度です。これに加えて、契約書の謄本(写し)の費用などが数百円かかります。書面にせず口約束で始める場合は、この費用はかかりません。
- 専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に依頼する場合の費用: ご自分で契約書を作成することもできますが、専門家にお願いすると、あなたの状況に合わせた最適な契約内容を相談したり、必要な書類を準備してもらったりと、スムーズに進めることができます。 この場合の費用は、依頼する内容や事務所によって大きく異なりますが、だいたい5万円から15万円程度が目安になることが多いです。これは、契約書作成や相談料としてかかる費用です。
2.実際に財産管理が始まった後にかかる費用
あなたが一時的に財産管理ができなくなり、受任者が実際に働き始めてからかかる費用です。
- 受任者の報酬(費用): あなたが選んだ受任者が、家族や親しい友人で、無報酬で引き受けてくれる場合は、この費用はかかりません。しかし、弁護士や司法書士などの専門家を受任者にした場合や、家族でも管理業務が多岐にわたる場合は、毎月報酬を支払うことになります。 この報酬は、管理する財産の量や、行う業務の内容によって変わりますが、月額1万円から3万円程度が目安となることが多いです。契約時に、報酬の有無や金額について、受任者とよく話し合って決めておくことが大切です。
このように、財産管理契約には、契約時と、実際に財産管理が始まった後の両方で費用がかかる可能性があります。
どんな人が「財産管理契約」を考えると良い?
- 高齢になり、少しずつお金の管理が不安になってきた方
- 一人暮らしで、急な入院や体調不良があった時に、誰かに財産管理をお願いしたい方
- 海外に長期滞在する予定があり、その間の国内の財産管理を任せたい方
- 子どもや家族が遠方に住んでいて、いざという時に頼れるか心配な方
- 本格的な後見制度はまだ考えていないけれど、将来の備えを始めたい方
- 任意後見制度の「入り口」として、まずは財産管理から試してみたい方
始めるには、どこに相談すればいい?
「財産管理契約、ちょっと考えてみようかな」と思ったら、まずは専門家に相談することをおすすめします。
- 弁護士(べんごし)さん
- 司法書士(しほうしょし)さん
- 行政書士(ぎょうせいしょし)さん
- 地域の役所の相談窓口(法律相談会など)
これらの専門家は、財産管理契約について詳しく教えてくれたり、契約書を作るお手伝いをしてくれたりします。いきなり契約する必要はありません。まずは「話を聞いてみたい」という気持ちで、気軽に相談してみると良いでしょう。
費用についても、事務所によって料金体系が異なるため、相談時にしっかりと見積もりを出してもらうことが大切です。
まとめ
財産管理契約は、将来の急な体調変化や、少しずつ判断能力が衰え始めた時に備えて、あなたが元気なうちに、あなたの財産管理を信頼できる人に託すための、柔軟な仕組みです。
メリットとしては、柔軟性があり、家族の負担を減らせること、そして比較的費用を抑えられる場合があることなどが挙げられます。しかし、本人の判断能力がなくなると使えないことや、医療行為など身の回りに関わることはカバーできないという注意点も理解しておく必要があります。
この制度を上手に活用して、あなた自身が安心して、そして大切な家族が困らないように、今から準備を始めてみませんか?
気になることや、さらに詳しく知りたいことはありましたか?
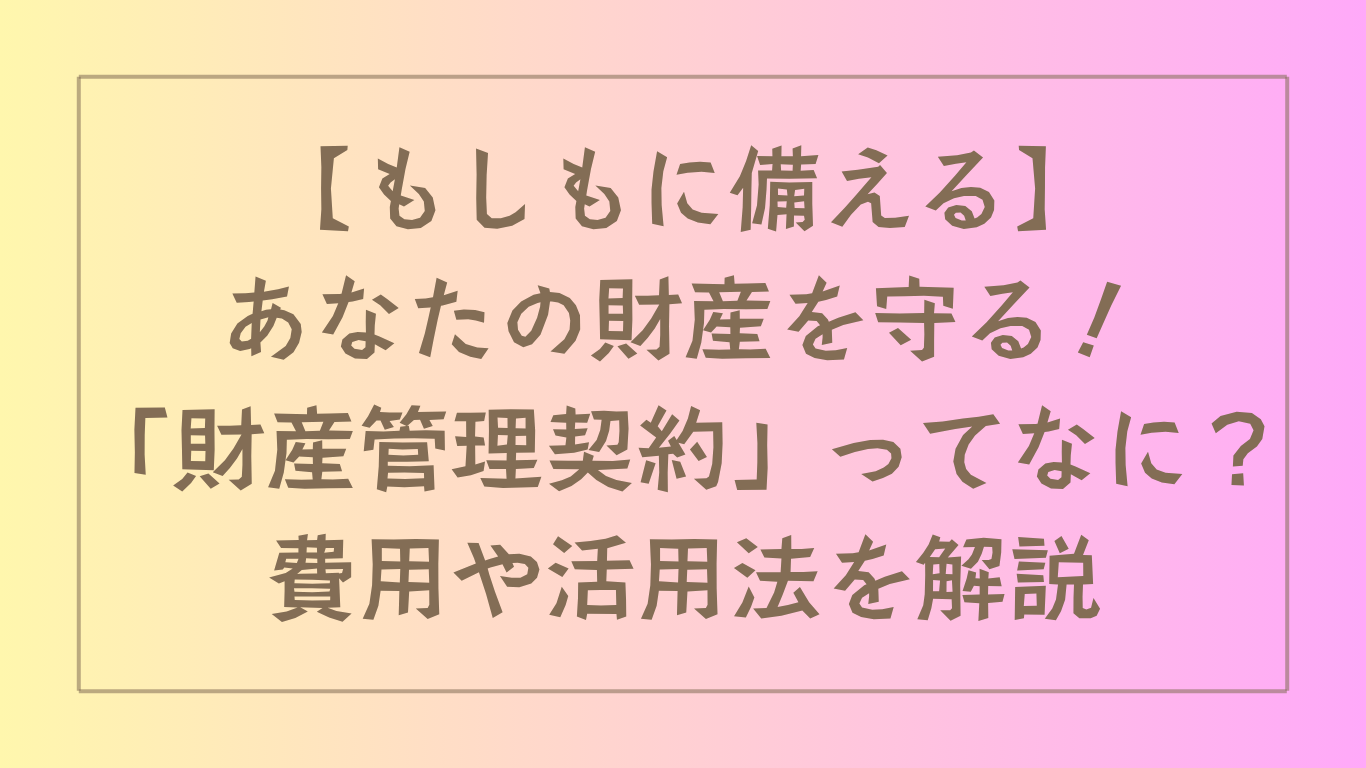
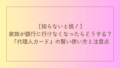
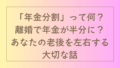
コメント